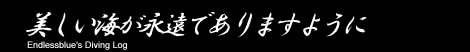魚類写真集
大瀬崎ダイビング 「ガラスハゼの幼魚」 Bryaninops yongei - 2009.11.07
黄金崎ダイビング 「ソラスズメダイ」 Pomacentrus coelestis - 2009.10.27
黄金崎ダイビング 「ハナタツ」 Hippocampus sindpnis - 2009.10.25
黄金崎ダイビング 「アミメハギ」 Rudarius ercodes - 2009.10.20
黄金崎公園ビーチでのダイビング。
お世話になったのは、デューク山中さん率いる「安良里ダイビングセンター」さんと、「海風通倶楽部(かいぶつくらぶ)」さんです。
この日の黄金崎公園ビーチは、午前中は20mはあろうかという透明度だったのですが、お昼前から濁りとうねりが入り始め、午後はかなりうねりが入ってしまうような状況でした。
そんな中、十分2本のダイビングを楽しむ事ができました!
ネジリンボウやキンギョハナダイ、スズメダイやネンブツダイ・・・沢山の魚が群れていますが、中でも目をひいたのが、このアミメハギの幼魚です。
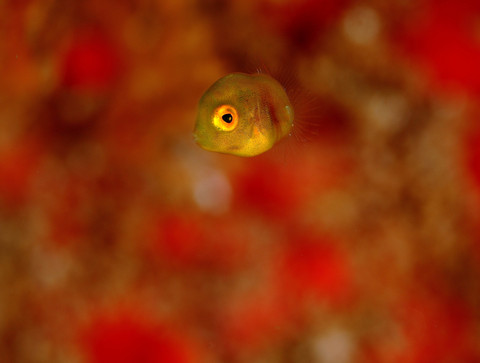
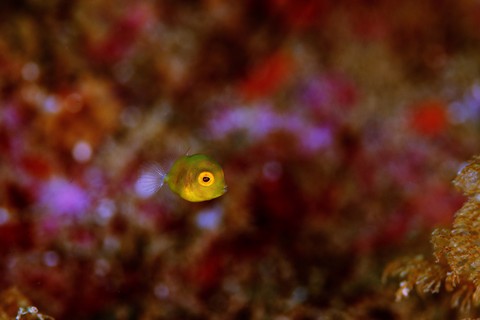
もうたまらなくかわいいでしょ!?
体長は、なんと1cm。
ふわ~・・・ふわ~~~
・・・っと漂っています。
もう、最高にカワイイ!
癒されますねぇ。
黄金崎ダイビング 「ネジリンボウ」 Stonogobiops xanthorhinica - 2009.10.18
この日は、新橋BOXさんの社員旅行に相乗りさせていただいて、西伊豆 黄金崎公園ビーチにダイビングに参りました。BOXさん、ありがとうございました!とても楽しいダイビングでした。
黄金崎公園ビーチといえば、なんといっても「ネジリンボウ」ですよね。
真っ白な海底に数箇所、ネジリンボウの巣穴があり、ダイバーに判別できるように、小石で囲んでストーンサークルが作ってあります。
全ての巣穴にネジリンボウがいるわけではなく、台風や海況の影響で、いなくなってしまったものや、ダイバーに蹴っ飛ばされて?巣穴が壊されてしまったものなど、いろいろです。
この日も、3つあったストーンサークルで、唯一、ひとつだけネジリンボウを発見する事ができました。
ところが、安心したのもつかの間、近寄ろうとするとすぐに引っ込んでしまいます。
皆さん、ネジリンボウに近づいて撮影する時は、2m以上手前で停止。
着底後、匍匐前進が基本ですよ~。
フィンキックで近寄ろうとするとすぐに感づかれてしまいますよ。
こうなると、さぁ大変。
15分近く待ったでしょうか?
あまりに粘るので、一緒に潜っていたチームは、皆違う場所に移動してしまいました(本当に申し訳ない・・・)。
DECOがあと5分というギリギリの状態で、ようやく出てきてくれました。

出てきてくれてホッとしました。
これほど待っても出てこなかったら、洒落になりませんものね。
ご覧のように、ネジリンボウは、テッポウエビの仲間と共生しています。
テッポウエビがせっせと穴を掘り、巣穴の外に砂を書き出しているのが分かりますか?
テッポウエビが仕事をしている間、ネジリンボウが見張りをしているというわけなのです。
仲がいいですね。
20枚ほど撮影し、その場をゆっくりと、静かに立ち去ります。
近寄る時と同様に、フィンキックでその場を離れてはいけません。
巣穴がふさがってしまいます。
ゆっくり後ずさりした後、BCにエアーを入れ、1~2mその場で浮き上がった後、移動するようにしましょう。
そうすれば、砂を巻き上げることなく、静かに移動できます。