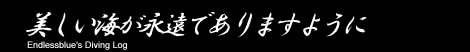大瀬崎ダイビング
ニシキウミウシ と ウミウシカクレエビ Ceratosoma trilobatum - 2009.11.23
晩秋の大瀬崎。
気温はグッと下がって16度。
でも水温は、下がっても19度。水面近くは21度あります。
この日は、外海ポイントの門下(もんした)が人気スポットでした。
ウミウシカクレエビが沢山発見されているのです。
ウミウシカクレエビ(Periclimenes imperataor)
伊豆より南の温かい海で多く発見されるエビです。
隠れ家としている母体は、伊豆の場合、ウミウシよりもナマコのほうが圧倒的に多いです。
アカナマコを見つけたらじっと観察してみると、見つかるかも知れませんね。
この日は、ラッキーな事にニシキウミウシに乗っているウミウシカクレエビを撮影する事ができました。
( ダイビングハウスマンボウのY君、Thank You ! )
でも、ニシキウミウシって身体が大きい分、移動距離が長いですし、移動するスピードも速いですよね。ウミウシカクレエビは、じっとしているのが好きらしく、ニシキウミウシが移動すると別の母体を探し始めます。
案の定、翌日には、ウミウシカクレエビは行方不明になっていました。
きっとどこか別の場所に旅立ってしまったんですね。
大瀬崎 ニシキリュウグウウミウシ属の一種1 Tambja sp. 3 - 2009.11.21
大瀬崎 肉食性の根魚 アナハゼとカサゴ - 2009.11.18
ツノザヤウミウシ Thecacera picta 大瀬崎 - 2009.11.14
大瀬崎・湾内のケーソンで発見。
このヒドラが大好物なんですよね。
いつも同じ場所にいます。
ツノザヤウミウシ(Thecacera picta)は、ミズタマウミウシ(Thecacera pennigera)のカラーバリエーションと解説している図鑑もあります。
この写真、良く見ると、もう1個体ウミウシがいるの分かりますか?
そう、ツノザヤウミウシのすぐ下に、小さなオレンジ色をした・・・
小さくてよく分かりませんが、たぶんエダウミウシ(Kaloplocamus ramosus)じゃないかなと思います。
こちらは、ウデフリツノザヤウミウシ (Thecacera pacifica)。
通称、ピカチュウ。
大瀬崎の人気者です。
今年も大発生中。