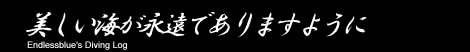大瀬崎ダイビング
大瀬崎のウミウシ 小さなピカチュウ - 2009.11.07
大瀬崎・湾内でのダイビング。
少しずつ水温が下がり始め、ウミウシを発見する確率も徐々に上がってきました。
小さな小さな、ウミウシたち。
かわいいですね。
ウデフリツノザヤウミウシ(Thecacera pacifica)
1cmに満たない、小さなウデフリツノザヤウミウシ(通称:ピカチュウ)です。
これだけ小さいと、ほんとにピカチュウってかんじですよね。
ヒドラにぶら下がって、お食事中でした。
シラユキウミウシとキイボキヌハダウミウシ
これまた、小さな・・1cmに満たないシラユキウミウシ(Noumea nivalis)。
なにか形が変だな?と思いながら撮影したのですが、パソコンに落としてみると、なんとキイボキヌハダウミウシ(Gymnodoris rubropapillosa)が喰らいついているではありませんか。
キイボキヌハダウミウシは、まるでドラキュラのように、他のウミウシに噛み付き、体液を吸い取るという吸血ウミウシです。
うわ~・・・こんな小さくても、やっぱり他のウミウシに喰らい付くんですね。
いや~びっくりです。
大瀬崎ダイビング 「ガラスハゼの幼魚」 Bryaninops yongei - 2009.11.07
大瀬崎ダイビング 「キヌヅツミの仲間」 Phenacovolva philippinarum - 2009.11.07
大瀬崎のウミウシ 「ガーベラミノウミウシ」 Sakuraeolis gerberina - 2009.11.06
大瀬崎・大川下ポイント。
先日の台風18号の本土上陸で、大川下ポイントの様子がまったく違うものになっていました。
まずエントリー口のスロープは、大ダメージ。
ゴロタ場も大きく変化しています。
まったく台風のパワーって凄いですね。
スロープが使用できないので、ゴロタの海岸をそろそろと降りてエントリー。
黒潮が入った、真青で透明な海を、中層をキープしながら進みます。
普段でしたら、中層を泳いでいる時に、海底が見えないので不安になるものですが、この日は、くっきりと海底が見渡せる感じ。
まさに大空を飛んでいる感じでした。
水深37mにある大きめの岩場には、たくさんのウミウシを見つけることが出来ました。
水深が深いので、長時間粘るわけにいきません。
数カット撮影し、浅場へと引き返します。
このガーベラミノウミウシ。
センナリウミヒドラに取り付いてお食事中です。
見える背面の突起には、消化腺が透かして見えます。
捕食しているセンナリウミヒドラの色に染まっていますね。
大瀬崎のウミウシ 「ゴマフビロードウミウシ」Jorunna parva - 2009.11.06
大瀬崎・先端ポイントで観察したゴマフビロードウミウシです。
この日の大瀬崎は、南西の風が強かったのですが、黒潮の流入の影響で物凄く透明度が良く、素晴らしいダイビング日和でした。
「ダイビングハウスマンボウ」さんのガイドで観察しました。