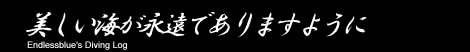大瀬崎ダイビング
大瀬崎ダイビング 湾内 「ワレカラモドキ」 Protella gracilis - 2009.04.22
大瀬崎湾内でのダイビング。マンボウ桟橋前からエントリーし、ロープに沿って潜行。一路ケーソンへ向かいます。途中、ガイドロープには、水温が上がって大繁殖中のシロガヤが生い茂ってます。
シロガヤに住むワレカラモドキ Protella gracilis
シロガヤの中をじっと見つめると、なにやら動くものが・・・
そう、ワレカラです。
体長は1cm未満。とても細い体をしています。
デジイチを使ったマクロ撮影の練習には、最適なターゲットです。
シロガヤの触手(シロガヤは植物ではなく、刺胞動物門ヒドロ虫の仲間です)部分にピントが合ってしまうので、なかなかワレカラに焦点が合いません。
偶然、焦点が合っても、とても小さいので確認が出来ません。
さらに、シロガヤは刺胞動物ですので、毒を持っています。
顔や手を近づけてもし触れてしまうと、痛みや痒み等の炎症を起こしてしまいます。
また、グローブに刺胞細胞がついてしまうと、そのグローブで顔をなでたりなどしたら大変。
そういう緊張感の中、いかに、うまく撮影できるか。それが練習になると思い、沢山シャッターを切ってみました。
ようやく、ワレカラが正面から撮れました。
やはりピントがいまひとつあっていません。
このあたりは、次回以降の練習テーマとしたいと思います。
とても海の生物とは思えない体つきをしてますよね。
エイリアンのような雰囲気。カマキリのような体。ワレカラっておもしろいですよね。
大瀬崎・湾内でのダイビング 「ヒメクロモウミウシ」 Aplysiopsis minor - 2009.04.22
大瀬崎・湾内でのダイビング 「オキゴンベ」Cirrhitichthys aureus - 2009.04.22
大瀬崎に限らず、伊豆周辺の海にはオキゴンベが沢山います。
ダイバーにとってオキゴンベはとても縁の深い魚。
ダイビングを習いたての頃は、限られた水深までしか潜る事ができませんが、練習を積み重ねる事によって、20m~30mと深い海に潜ることができるようになります。そうすると、このオキゴンベに会えるようになるのです。しかも、水中での写真撮影に興味が出てくると、オキゴンベの写真が撮りたくてたまらなくなります。
【オキゴンベが被写体に好まれる理由 その1】
根魚なので、基本的にはじっと動きません。ですから、ダイバーが写真を撮りやすいようにじっとしていてくれるのです。でも、不用意に近づくとパッと逃げてしまいますから、ダイビングテクニックも自然と上達しますよね。
【オキゴンベが被写体に好まれる理由 その2】
漁礁など、ここはというポイントには必ずオキゴンベがいるのですが、どこにいるかな?と探さなくてもひょこっと顔を出してくれる。オキゴンベのほうから挨拶してくれている感じです。
いい奴ですよね。
【オキゴンベが被写体に好まれる理由 その3】
背中の背びれが特徴的。ぴょいぴょい、とツンツン飛び出る背びれが可愛く、初心者ダイバーにとって「へぇ~~、こんな魚見たことない。」と、とても被写体としてGoodなのです。ちなみにこの背びれのツンツンが名前の由来になっているそうです。江戸時代には、小さな赤ちゃんの髪型は、うなじの部分に少しだけ毛を残して、あとは剃ってしまう髪型がありましたが、それを「権兵衛」というのだそうです。
【オキゴンベが被写体に好まれる理由 その4】
なんといっても、オレンジのボディにグリーンの眼がとても美しい。写真に写すとその美しさがより際立ちます。
大瀬崎・湾内でのダイビング 「ミジンベニハゼ」 Lubricogobius - 2009.04.21
大瀬崎湾内。ダイビングハウスマンボウ前の桟橋から、左方向。
第2漁礁~第3漁礁の奥の砂地から泥地に変化する辺りで発見しました。
本当は、キアンコウがいないかな?と砂地を探していたところ、ピコっと顔を出したのがこいつです。
「ミジンベニハゼ」 Lubricogobius
本当は、もっとじっくり狙って、真正面からのアップを狙いたかったのですが、何せ、減圧限界が・・・。この手の被写体をじっくり狙うには、1本目に狙わないとダメですね。
このあたりのポイントには、ミジンベニハゼが沢山いるようです。以前、巻貝から顔を出している子と見たことがありますが、できれば、人工物ではなく、自然のものを住みかにしている子を写したいですね。